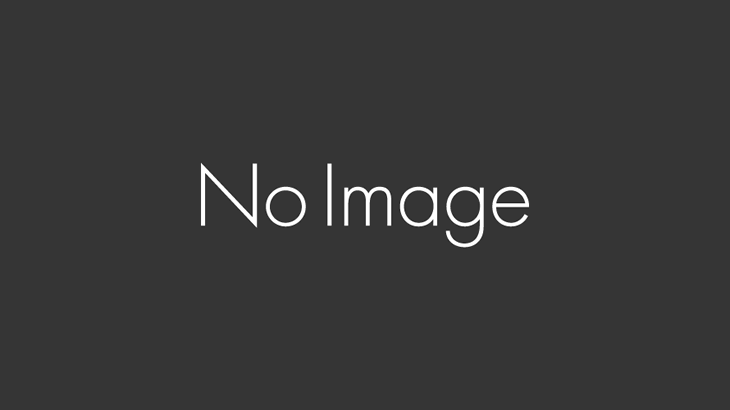敵は老眼…
(再び)Estron Linum 2pin Bax-dual twist 8000057 を購入したった
つい先日購入したEstron Linum BaX dual twistですが、挑戦したかった工作をするために分解しました。
estron Linum MMCX Music 8000060 リケーブル購入
以前購入して気に入っていた同じくEstron Linum Music(MMCX)と違いBaXは左右のケーブルがプラグまで各2芯で独立してます。
(Musicは分岐部からプラグまではグランド共通で3芯)
ということで、Linum Musicではできない4極バランス化が可能ってことになります。
これを今さら気が付いてしまってので購入したんです。
黒いアウター部を取り外しました。
がっちり固定されているので、再利用はできないかと思いカッターで分解を。
※デジカメを用意して写真を撮る元気がなかったので、iPhoneですませているので見にくくてすみません。
がっちり樹脂で固定されてます。
Limunは1本1㎜に満たない細さなので、これだけで固定できる訳ないのでこのくらいの方が安心できます。
Linumは断線に強い。と謳われていますが、それはケーブル単体での話ですので。
分解しました。
分解して気が付きましたが、この細さで強度を持たせるための繊維が入っているんですね…
これも分解して気が付いたことですが、Linumはリッツ線が6芯となってます。
HOT/COLDで3本ずつです。
※よくよく調べてみたら、サイトにも『- 6 litz conductors made up of 7 individual strands.』て、書いてあった。
で、問題です。
どれがHOT線ですか???
HOT3本、COLD3本合わせて撚ってます。
ショートしないのはそれぞれシース代わりに塗装(なのかな?)がされているからです。
そんな処理がされているので、どれがどの線なのかをテスターで調べるのはちょっと手間でした。
ライターとかで熱を加えれば塗装も溶けてリッツ線が剥き出しになるのでしょうけど、それですと組み付けるときに問題になるので、切断した部分だけをテスターに当てて1本1本確認しました。
この確認作業だけでえらい時間がかかった…
まだまだ2.5㎜4極プラグは少ないので、以前も使ったBispaのプラグを今回も使うことに。
老眼なぼくには辛いサイズ…
ピンアサインについては以前の記事をご参考に。
ピンぼけすぎて参考になりませんが…
最初から芯線を短くしてハンダ付けすると失敗するかなと思いある程度の長さでハンダ付けをしてから余分な部分を切断しました。
撚線そのものが細いので、その方法でも邪魔にならずよかったです。
ただ相変わらずハンダ付けする場所が小さいので、隣接したところで短絡してしまうこともあるので注意が必要です。
その場合は余分なハンダを落とせばいいだけですけど。
この時点で通電確認と短絡をしてしまい、問題がなかったのでエポキシ接着剤で固定をしました。
寝ぼけながらの作業だったので、ここでもピンアサインの間違いや、そもそも左右を間違えていないかとしっかりを確認をしました。
特に、ケーブルが動いたときに撚り線が隣の端子に触れるということがないかの確認が重要だったので、きちんと時間を掛けて調べました。
上の状態ではエポキシで軽く固定してます。
これで短絡してないかをあらためて確認して次はしっかりと固定することにします。
なんかエポキシが固まるのに時間が掛かり変な形になりましたが、左右のケーブルをプラグで固定してます。
これで、ハンダで固定した部分に負荷が掛かるのではなくて、ケーブルそのものをエポキシで固定した形になるので、断線に対してある程度強度が取れたと思います。
ですが、やはり寝ぼけていたのか色々と処理をするのに寸法が間違っていたりして狙った形になりませんでした。
手前の黒いのは端子ショート防止用のゴムカバーみたいなものを切断したものです。
ぼくはこれを使ってケーブルがフラフラするのを防止する加工をするんですが、プラグの寸法とケーブルが細いということを忘れててあまりに小さくし過ぎました…
あんまりというか、まったく意味をなしてない。
とはいえ、とりあえず完成。
音出しも確認。
音は出ていたので問題ないだろうけど、もう一度短絡してないかなどを確認。
プラグ部分をぐりぐりしながら確認したけど特に不具合はない。
これで当初の目的は達した。
色々と準備不足と老眼により作業は無駄に時間が掛かった。
年末からやりたかったことはできたし、ケーブルが無駄にならずにちょっと安心した。
約1万円というリケーブル界では比較的安いものではあるけど、失敗したらぼくとしては痛い。
じゃあ、音はどうか?
僕クロが行方不明なので、疑似バランスのAK100でしか確認できませんが、4極化に伴うクロストーク削減で左右の音場の広がりは良くなった。
ですが
元々BaXの性格から、Musicと違う上と下を持ち上げた音なので、フラット系を好むぼくからしたらちょっと聞きにくい(声が遠い)
Linum Musicの音でdual twistしてほしいですね。
それでも狙った効果は出ているのでしばらく聞いていれば、耳エージングも進むでしょうからこれでいいでしょう。
世の中(偏った世界)では、太さこそ命みたいな風潮がありますが、Estron Linumのケーブルは素直な特性とほんと良いケーブルだと思います。
取り回しでこれを超えられるものはないでしょう。
ちょっとリケーブルしてみようかなと思ったとき、特に2.5㎜4極のものを選択しようとすると軽く3万はします…
1本基本のケーブルとしてほしいなとは思ったんですが、さすがにそこまでのものは手が付けられません。
加工し難いですが、できない訳ではないというのがこれで証明できたので満足。